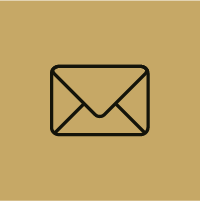置き方ひとつで、仕上がりが変わる
新人家具職人の気づきノート |memo_003
家具職人として働きはじめてから気づいたのは、「技術」や「道具」も大切ですが、その前段階にある“準備の仕方”が作業の精度やスピードに大きく関わっているということでした。
材料の置き方や並べ方、使う順番、そして「どこを基準にするか」。それらに気を配るかどうかで作業の進み方も、仕上がりの美しさも、大きく変わってきます。
今回は自省の意味も込めて「材料の置き方や順番が、作業の精度にどう影響するか」ということを書きたいと思います。
たとえば、板材を切り出して並べるとき。
反りや木目の向きを確認せず、ただ何となく積んでしまうと、次の工程で「これはどっちが表だっけ?」「反ってる?」といちいち確認することになり、流れが止まります。
実際、最初の頃はそうした場面の連続でした。
作業に集中しようとしても、どこかに迷いがあると、思考も動作も止まってしまう。

今は作業に入る前に、「どの順番で使うか」「どちらの面が表か」「木目の流れはどうか」「組み立てたときの上下左右はどうなるか」などをざっと確認してから、材料を並べ直すようにしています。
まだ癖づけの途中ですが、これをやるだけで、作業がぐっとスムーズになる実感があります。
手戻りや確認の手間が減って、「考える」よりも「手が動く」状態に近づく気がします。
材料の順番も、思っていた以上に大事なポイントでした。
木取りや下穴あけなど、流れのある作業では、材料が順序よく並んでいるだけで、体の動きが自然になります。
逆に、順番を意識せずに作業すると、「これ加工済んでたっけ?」と確認が増えたり、何度も往復することになったり。
動きの流れが途切れると、ちょっとしたストレスや疲れにもつながるのだと気づきました。
そしてもう一つ、大きな気づきだったのが「勝手墨(かってずみ)」の考え方です。
入社して初めて知った言葉でしたが、「どの面・どの方向から寸法を取るかをあらかじめ決めておく」ことで、ズレや誤差を防ぐというもの。

最初はなんとなく線を引いていましたが、ほんの1mmのズレが、組み立てや仕上げに大きく影響することを経験してから、意識が変わりました。
今では、「この面が基準」「この方向で寸法をとる」と自分の中で決めてから墨をつけるようにしています。
勝手墨の向きもできるだけ揃える。
ほんの少しの意識ですが、それが積み重なることで、仕上がりに差が出てくるのだと思います。
五味さんの仕事を見ていると、作業の手際の良さにも驚きますが、実際に手を動かす前の段取りの時点で、すでに仕事の精度が決まっているように思えます。
材料の置き方、順番、勝手墨。
どれも一見些細なことだけれど、これらを“整える”ことが、結果として作業の精度と効率を高めてくれる。
逆にここを疎かにすると、「探す」「戻る」「確認する」という無駄な動きが増えてしまい、集中が途切れやすくなる。
つまり、作業は“始める前”にすでに結果が決まり始めているのだと思います。
こうした気づきを得る中で、ふと「料理に似ているな」と感じました。
食材の向きや順番を考え、まな板や鍋を整えてから作業に入る。
準備が整っているからこそ、味つけや火加減にも集中できて、仕上がりまで気持ちよく進められる。
家具も同じで、段取りが整っていると、その先にある“仕上がり”に、手と気持ちを注げる余裕が生まれる。
まだまだ試行錯誤の毎日ですが、今日も丁寧に「始める前の準備」から向き合っていきたいと思います。